2021年に行われた登録販売者試験の合格率と出題傾向
2021年12月8日
2021年に行われた登録販売者試験の合格率と出題傾向
※こちらの記事は2021年11月17日に書かれたものであり、現時点で奈良県、中国ブロック、四国ブロック、三重県、九州・沖縄ブロックの合格発表前、もしくはこれから試験が行われます。合格率が出ましたら、また加筆・修正いたします。
1.登録販売者試験のブロックについて
登録販売者試験は、毎年、全国を数ブロックに分けて行われ、ブロックごとに試験問題が異なります。つまり、同ブロック内の試験問題は同じです。ただし昨年から、新型コロナウイルス感染拡大の影響により試験が延期される都道府県も出ており、別の日程のブロックに統合されるケースも生じています。このように少し例外があるものの、現在のところ、ブロックの構成は次のようになっています。
- 北海道・東北ブロック:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
- 関東・甲信越ブロック:茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 山梨県 長野県
- 首都圏ブロック :東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県
- 北陸・東海ブロック :富山県 石川県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県
- 関西広域連合ブロック:大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 和歌山県 徳島県 福井県
- 奈良ブロック :奈良県
- 中国ブロック :鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
- 四国ブロック :香川県 高知県 愛媛県
- 九州・沖縄ブロック :福岡県 大分県 宮崎県 佐賀県 長崎県 熊本県 鹿児島県 沖縄県
2.2021年の登録販売者試験【ブロックごとの合格率】
2021年の登録販売者試験は、現時点、2020年よりも合格率が上昇したブロックがほとんどです。試験の難易度も全体的に少し下がり、基本的な知識を問う出題が増えている傾向があります。例外的に北海道・東北ブロックは合格率が下がっていますが、こちらの理由については後述します。
【ブロック別 合格率ランキング】
| 順位 | ブロック | 2021年の合格率 | 2020年の合格率 | 2020年との合格率の比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北陸・東海ブロック ※三重県は延期のため除外 |
56.3% | 50.8% | 5.5ポイント上昇 |
| 2位 | 関西広域連合ブロック | 55.9% | 39.5% ※福井県はほぼ同じ問題だったため合算 |
16.4ポイント上昇 |
| 3位 | 関東・甲信越ブロック | 46.9% | 39.8% ※関東ブロックと甲信越ブロックで別日程だが合算 |
7.1ポイント上昇 |
| 4位 | 首都圏ブロック外 | 43.6% | 33.9% | 9.7ポイント上昇 |
| 5位 | 北海道・東北ブロック | 40.4% | 43.0% ※北海道ブロックは別日程のため除外 |
2.6ポイント減少 |
3.2021年の登録販売者試験【ブロックごとの出題傾向】
・①北海道・東北ブロック
北海道・東北ブロックでは、特に第4章の問題に難化傾向が見られました。たとえば問85は実在する商品の成分表を見ながら答える問題ですが、「濫用等の恐れのある医薬品」や「店舗における掲示」、「指定第二類医薬品の陳列」など、複合的な知識を一度に問う良問でした。このほかにも、少し立ち止まって考えさせるような問題がいくつか出題されています。
「想定外の問題」や「難しい問題」は、必ず毎年、どのブロックでも出題されます。このような問題に出くわしたときに一番もったいないことは、その問題で心を挫いてしまい、その後の「いつもなら落とさない問題」をも落としてしまうことです。これを防ぐためにも普段の勉強で過去問を解くときに心がけてほしいことは、どのような問題が出ても「ほほう、そう来ましたか...」といった具合に軽く受け流す力を付けることです。もしくは、そのような問題に出くわしてしまったときに、どのように心を落ち着かせるか(いったん鉛筆を置いて深呼吸するなど)を前もって決めておくことが大切です。
・②関西広域連合ブロック
2020年の関西広域連合ブロックの試験では、第3章で接客の様子を取り入れた新傾向の漢方薬の問題が出題され、合格に一歩届かなかったという人が続出しました。2021年の第3章の問題では、このような新傾向の問題は姿を消し、漢方薬の問題も非常にスタンダードなものに戻りました。他の章に関しても素直な問題が多く、全体的に解きやすい傾向となりました。
・③北陸・東海ブロック
例年、比較的安定した合格率を誇る北陸・東海ブロックですが、2021年も同じような傾向が続いています。第2章では細かな知識を問う問題も散見されましたが、全体的に素直な問題が多く、例年通り基礎力があれば合格しやすい傾向となりました。
・④関東・甲信越ブロック
例年、特に第4章にクセのある問題が含まれている傾向がありますが、2021年の試験ではそのような問題はほとんどありませんでした。また、関東・甲信越ブロックだけでなく全国的な傾向となりますが、第3章と第5章において、商品の配合成分表を見ながら答えていく問題が増えています。実際に登録販売者として医薬品の接客をする際には、パッケージに書いてある成分名を見ながらどのような商品かを説明するため、このような形式の問題は接客の予行練習ともいえる出題です。ぜひこの形式の問題にも慣れておきましょう。
【成分表形式の出題の例】
問1 次の表は、ある一般用医薬品のアレルギー用薬に含まれている成分の一覧である。このアレルギー用薬に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(2錠中)
- メキタジン 4mg
- リボフラビン 12mg
- ピリドキシン塩酸塩 30mg
- ニコチン酸アミド 60mg
- a. ○○である
- b. △△である
- c. □□である。
- d. ✕✕である
1( a , b ) 2( a , c ) 3( b , c ) 4( b , d ) 5( c , d
・⑤首都圏ブロック
首都圏ブロックは、ここ数年合格率の低い状態が続いていましたが、今年は合格率が上がりました。首都圏ブロックは全国の中でも生薬・漢方薬の記述が含まれた問題が最も多く出題され、一時期は、このまま行くと第3章の全40問のうちの半数が生薬・漢方薬の記述が含まれた問題になってしまうのでは?と懸念されるぐらいの量でした。ところが今年は生薬・漢方薬の問題が、近年の試験に比べて3~4問ほど減りました。
また、首都圏の生薬・漢方薬の問題は、他県と比較して少々独特な出題形式になっています。首都圏以外のブロックでは、「1問の中の全ての記述が漢方薬・生薬に関するもの」という形式が多いのですが、首都圏の場合、「1問の中に1つだけ漢方薬・生薬の記述が含まれる」という出題形式が多く見られます。「分散式」とでも呼べばよいでしょうか。
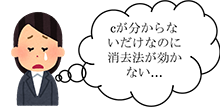
【首都圏の出題形式の例】
→分散式である
問1 次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか
- a. 西洋薬の記述
- b. 西洋薬の記述
- c. 漢方薬の記述
- d. 西洋薬の記述
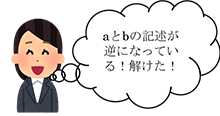
【その他のブロックの出題形式の例】
→まとめて出題される
問1 次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか
- a. 漢方薬の記述
- b. 漢方薬の記述
- c. 漢方薬の記述
- d. 漢方薬の記述
「分散式」の問題では頭を漢方薬モードに切り替えるのが難しい上に、他の記述をヒントにすることもできません。これにより、たった1つ混ざっている生薬・漢方薬に関する記述の正誤が分からないだけで、結果として1問まるまる落としてしまう状況が発生し、精神的ダメージが大きくなります。「分散式」の問題は、近年、他のブロックでもちらほら見かけるようになりましたので、首都圏以外のブロックを受験する予定の人も、首都圏の過去問題を解いて慣れておくとよいでしょう。
執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)
株式会社東京マキア 代表取締役
登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開
【新着】登録販売者のための業界コラム
- 2024年11月15日【現場で使える!漢方】登販向け:冷えを解消する漢方薬のおすすめは?
- 2024年08月21日登録販売者と調剤薬局事務どっちがいい?年収や仕事内容の違いを解説
- 2024年06月21日【現役ドラッグストア店長直伝】登録販売者こそ添付文書を読むべき<登録販売者のキャリア>
- 2024年05月21日【ドラッグストアの一日】お子さまへの解熱剤販売時に確認しておきたいこと
- 2023年10月20日【2023年最新】京都の登録販売者求人市場を徹底調査!理想の転職先を見つけるには


